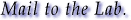|
|
|||||||
【これから学ぶ研究室を検討している諸君へ:”安藤研で勉強する”とは?】 ⇒ 2024年度 研究室所属(学部)を考えている諸君へ(訪問前にこのページをチェック) ★安藤研で修士課程修了まで指導できるのは, '24年度のM1生が最後となります. 現時点での学部3年生は、修士修了まで指導することができませんので,留意して下さい. |
|||||||
|
|
|||||||
| 研究室のモットー | ★違うやり方でやってみよう (Do Differently)★ この標語は,恩師の一人である英国Durham大学のRobin K. HARRIS先生から教えていただいたものです。研究者は人と違ったことを人と違ったやり方でをやるべきだ、という意味です。違うことをやっていれば、結果はあとからついてきます(←と思いたい)。 |
||||||
|
|
|||||||
| 本研究室でガンバレば こんな技能が身に付きます。 (研究室運営と指導の方針) |
① 機能性ポリマーの基盤研究を深め、実社会で活躍できる人材を育成します.研究室で自分の研究を遂行することは,テストの問題を解くのと異なり,複雑な問題(状況)をどのように解決していくかを日々自分のアタマで考え,判断しながら進めていくことを意味しています.研究活動を通じてこのことに気づき、自分のチカラで研究を進めることができるようになると、毎日の研究が楽しく、かつ“やり甲斐”のあるものになります.われわれの研究室では,研究成果そのものより,学生一人ひとりの問題解決能力をいかに高めるかを考えます.そして、そのためには(逆説的ですが)最先端の研究テーマに取り組むことがもっとも適しています.これまで誰も真剣に取り組まなかった問題こそが,問題解決の能力を育てるからです.また,研究室の指導方針として、研究者・技術者として、どのような現場に出ても使える”汎用性のある考え方”と”基本となるテクニック”、そして”高分子材料に対するセンスの良さ”も身につけて欲しいと思っています。それらは例えば、以下のようなことを指しています。 ② 自分の対象物質は基本的に自分で合成します.安藤研は機能性ポリマーの構造-物性相関を探究する研究室ですが,研究対象の試料は,(ほぼ)自分たちで合成します。機能性高分子研究をやる上で,合成の知識と経験はとても役に立ちます。もちろん,最終目的は物性・構造研究+機能性高分子の開発ですが,機器分析や計算だけで革新的な材料ができることは(めったに)ありません。一方,合成だけでは,その材料がもっている真の特性を理解して引き出すことが困難です。研究室の学生諸君には,ぜひ修士修了までに,分子設計(量子計算)→(モノマー合成→)ポリマー合成→機器分析→特性評価→分子設計のサイクルを最低1回は回してもらい,卒業後は「任されたら何でも出来る(と言える)研究者」になって欲しいと思っています。 ③ とは言え,われわれの研究室にはたくさんの分光計測器(研究設備を参照)があります。在学中に少なくとも3つ以上の分光器を完全に使いこなすことで、各種スペクトルの測定原理・測定技術・そして高度な解析技術が身に付きます。市販の装置を買ってきてそのまま分析に使うことはめったにありません。ほとんどの計測機器は自分たちで組み立てるか、市販の装置に改造を加え、一般の研究室では測定できないようなやや特殊な物性の測定を目指します。こうすることによって,他の研究室では得られない貴重なデータが集積でき,それに基づいた革新的な材料設計ができると考えています. 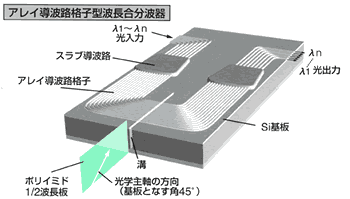 例えば,右に示したポリイミド1/2波長板(緑の部分)は,私がNTT研究所時代に開発した光学部品で,海外の光通信ネットワークで広く使用されています(日本は光ファイバ通信の発明国で,その性能が良すぎるため,まだ使われていない).光導波部品用の薄型波長板として1995年当時は,水晶製しかありませんでしたが,これを含フッ素ポリイミド製にすることによって光損失が1/10以下となり,操作性や経済性も格段に向上し、世界中で使われるようになりました.この材料を開発する過程では,ポリイミドの延伸装置や光学測定装置を若手社員と2人で設計し,大量生産ができるところまで持って行きました。このようなテーマに遭遇したのは本当に幸運でしたが,チャンスは基本的に誰にも平等に訪れます.研究室の学生諸君には、若いウチに是非私と似たような"成功体験"をして欲しいと思っています。 例えば,右に示したポリイミド1/2波長板(緑の部分)は,私がNTT研究所時代に開発した光学部品で,海外の光通信ネットワークで広く使用されています(日本は光ファイバ通信の発明国で,その性能が良すぎるため,まだ使われていない).光導波部品用の薄型波長板として1995年当時は,水晶製しかありませんでしたが,これを含フッ素ポリイミド製にすることによって光損失が1/10以下となり,操作性や経済性も格段に向上し、世界中で使われるようになりました.この材料を開発する過程では,ポリイミドの延伸装置や光学測定装置を若手社員と2人で設計し,大量生産ができるところまで持って行きました。このようなテーマに遭遇したのは本当に幸運でしたが,チャンスは基本的に誰にも平等に訪れます.研究室の学生諸君には、若いウチに是非私と似たような"成功体験"をして欲しいと思っています。④ 材料としての各種物性(光学物性、電気物性、熱物性、機械物性など)を高分子の立体構造と電子状態から理解し予測するマインドが身につきます。これは私の恩師である安藤勲先生から受け継いだもので、高分子を化学式や化学構造のような平面的なものではなく、常に3次元的な構造を持ち、その裏にある波動関数(電子状態)がすべての物性を決定する、ということを常にアタマにイメージして、高分子材料を理解しようと試みます。 ⑤量子化学計算による物性の予測を重視します。ですので、多くの学生が密度汎関数法(DFT)を用いた分子科学計算に習熟しています。安藤研は量子化学の研究室ではありませんが,常にTSUBAME 3.0の大口ユーザです.大規模な数値計算に必要なワークステーションやUnixなどのOS、プログラミング言語の知識も身につきます。また、②で示した各種分光器も、学生自らが測定制御の新たなアルゴリズムを考案し、Visual Basic のようなコンピュータ言語で制御プログラムを書き、そしてデータ解析までを自動化することを目指しています。 ⑥ 以上のことをひととおり学んで自分の実力とするためには、一生懸命努力するのは当然としても一朝一夕では難しく、それなりの時間がかかります、ですので、私たちの研究室では大学院への進学希望を有する学生を優先的に受け入れたいと考えています。博士課程への進学希望者も歓迎します。 ⑦ 一方、社会にでたら、聴衆の前でのプレゼンテーション能力と英語でのコミュニケーション能力は不可欠です。学生諸君はほぼ毎月まわってくる研究報告会と、年3~4回の国内学会発表(口頭発表優先)で、高いプレゼンテーション能力と完璧なスライド作製(パワーポイント)術を身につけていきます。学会への派遣回数と発表数の多さは応化系内でも有数です(最近の国際学会・国内学会発表を参照)。また,ほとんどの学生が修士課程修了までに海外の国際学会で,英語で口頭発表する経験をしています。研究室内でのTOEIC受検奨励制度、海外の国際学会への派遣(博士学生はほぼ毎年)、海外短期留学(3~6ヶ月)やAOTULEやMISW(東工大工学系の国際学生ワークショップ)への参加支援、海外研究者の招聘や交換大学院生の滞在などで、英語でのコミュニケーション能力向上を目指しています。また、危険物取扱主任者、特定化学物質・有機溶剤取扱主任、第一種衛生管理者など社会に出て役立つ資格は、自ら受検して合格すれば受検料を補助しています。 ⑧ 加えて、社会には同年代だけのグループなど存在しませんから、年齢の異なるグループ内でのリーダーシップや協調性も不可欠です。これら完璧だと,社会では勉強や研究以上に高く評価されます。 |
||||||
|
|
|||||||
| 安藤研に所属する 学生に期待すること |
①(何ごとに対しても)好奇心を持とうとすること。(高分子科学にとどまらず)一生のうちに“世界という書物“を理解したいと考えていること。 ② “高分子の立体構造・電子状態と物性の相関“に興味があり,その理解を通して,またその基盤技術を身につけて新たな機能性ポリマーを世に送り出したいと考えていること。 ③ 国際共同研究に興味があり,東工大在学中に海外での研究発表や共同研究をやってみたいと考えていること(”漠然とした希望”でも良い)。 ④ (東工大の学部生は)「高分子物理1~4」と「高分子特性解析」を履修して,それらの内容をおおむね理解していること(研究室で先輩と復習するので,一部は未履修でも良いが,これらの課目が嫌いだと研究室に入ってから少し困ると思う)。 ☆ 高岡市立 伏木中学校の歌「風はどこから吹いて来る」(堀田善衞 作詞) 風はどこから吹いて来る 丘を吹く風 海の風 風はどこから吹いて来る 丘を吹く風 海の風 港の町に育つ仕合せは 風の故郷と行く先を マストの鴎とともに知る 倉庫の陰で働く人も ウインチ巻いて荷揚げの人も みんな行く手を知っている 広い世界で働こう 広い世界を知り抜こう たとえわれらの町の長い冬 海の色は暗くても その暗い重さはわれわれの 心の錨 学んで知るは羅針盤 さあ船出しよう エンジンかけて 広い世界で働こう 広い世界を知り抜こう 風はどこから吹いて来る 丘を吹く風 海の風 風はどこから吹いて来る 丘を吹く風 海の風 |
||||||
|
|
|||||||
| 卒業生の就職先 | ダウジャパン・三菱総合研究所・富士フイルム・東レ・住友化学・三菱ケミカル・村田製作所・野村総研・ニコン・信越化学・古河電工・クラレ・メディエンス・ROKI・DIC(大日本インキ)・JNC・太陽HD・数理計画・富士通・三井デュポンフロロケミカル・凸版印刷・JSR・帝人・旭化成・旭硝子・ポリプラスチックス・ソマール・パナソニック電工・河合塾マナビス・三菱レイヨン・三井化学・キャノン・リコー・BASFジャパン・日立製作所・東芝・三洋電機・日東電工・東急電鉄・三菱ガス化学・三菱商事・ラット(ITベンチャー) など。 ほとんどの学生は卒業後、企業の研究所に配属されるのが現状ですから、社会に出たあとの自分の姿を学生のうちからイメージしておくことは大切です。私も博士課程1年の夏休みにインターン制度に応募し、企業の研究所で4週間の研修をさせてもらいました。このときの経験は、その後の進路の判断にとても役に立ちました(研修中には成果がほとんど出ませんでしたが)。 現在、研究室では夏季インターン制度への応募を奨励するとともに、おもに研究室の卒業生(3~6年目)にお願いして、企業の研究所見学をさせていただいたり、研究室の先輩と語る会を催しています。 就職指導は特にしていませんが、学生達はみな自立しているので、行きたい会社を自分で探して行くようです。私は東工大の教員になる前,企業の研究所に6年3ヶ月,勤務していたので、どのような人材を企業は必要としているか、どのような意識で仕事をすれば成果を上げられるか、特許と論文の違い(企業での知的財産権の考え方)、企業での安全意識、職能制度や労働組合とはどんなものか、というような話は折をみてしています。 |
||||||
|
|
|||||||
| 見学にきませんか? | 安藤研の研究内容に興味のあり,われわれと一緒に研究してみたい学生は、一度、見学に来てください。オープンキャンパスも良い機会です.教員と院生が親切に説明します。見学に来る前にはできるだけメールで連絡してください。 |
||||||
|
|
|||||||
|
|||||||