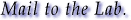|
|
|||||||
【学部3年・修士課程受験の諸君へ:安藤研・石毛研で勉強する”とは?】 研究室訪問の前に、このページを読んでおこう. |
|||||||
|
|
|||||||
| 研究室の 構成 |
 安藤研・石毛研では、自分たちで開発した新規の高分子分光法・分析法を駆使して、光機能・電子機能・熱機能性をもった新しい高耐熱性ポリマー(おもにポリイミド)を研究・開発しています.基礎・基盤的な研究から始め、実用材料として世の中に出せる少し前までの研究を目指しています.現在の研究領域は大きく4つにわけられるため、4つのサブグループ(SG)があり,2名の教員が共同で指導しています. 安藤研・石毛研では、自分たちで開発した新規の高分子分光法・分析法を駆使して、光機能・電子機能・熱機能性をもった新しい高耐熱性ポリマー(おもにポリイミド)を研究・開発しています.基礎・基盤的な研究から始め、実用材料として世の中に出せる少し前までの研究を目指しています.現在の研究領域は大きく4つにわけられるため、4つのサブグループ(SG)があり,2名の教員が共同で指導しています.★2023年度4月から、安藤研究室と石毛研究室は独立運営に移行しますので、受け入れる学生も別個に募集します. ① 蛍光・燐光物性SG:高蛍光性・高燐光性ポリイミドの合成と光物性制御、励起状態プロトン移動による新規高蛍光性物質の創製、ドナー・アクセプター構造を有する蛍光性ポリイミド,光デバイスや光インターコネクションを目指したフォトニクス・ポリイミドの開発など. ② 高圧・高温構造SG:超高圧印加によるポリイミドの構造・物性変化の解析、ポリイミドの熱膨張の分子論的基礎の理解と超低熱膨張ポリマーの分子設計・開発、ポリイミド系超熱電導・熱制御材料の開発など. ③ 液晶構造・配向物性SG:液晶性を示すポリイミド前駆体の分子設計と配向特性の制御,温度可変広角X線や偏光赤外スペクトルによる配向解析、自発配向現象を用いた新規配向膜材料の開発など. ④ 光学・電気物性SG:ポリイミドの屈折率・複屈折・熱光学係数の制御、ポリイミドの熱膨張の分子論的基礎の理解と超低熱膨張ポリマーの分子設計・開発、ポリイミド薄膜の暗電流・光電流特性の新規測定法の開発と解析など.  これらのサブグループ内では、作製・使用する測定機器や対象とする物性に共通点が多いことから、緊密なコミュニケーションをとって、勉強会や研究を進めています. これらのサブグループ内では、作製・使用する測定機器や対象とする物性に共通点が多いことから、緊密なコミュニケーションをとって、勉強会や研究を進めています. 安藤研では、研究対象とする物質は基本的に学生自身が合成します(一生懸命やれば、大抵できるようになります).難しい合成ではありませんが、がんばってもできないときは、合成系の研究室に派遣し,共同研究として指導していただきます. 安藤研では、研究対象とする物質は基本的に学生自身が合成します(一生懸命やれば、大抵できるようになります).難しい合成ではありませんが、がんばってもできないときは、合成系の研究室に派遣し,共同研究として指導していただきます. |
||||||
|
|
|||||||
| 研究室の 1年 |
 4月初め:4年生歓迎会 (手作り餃子・たこ焼きパーティなど). 4月初め:4年生歓迎会 (手作り餃子・たこ焼きパーティなど). GW:研究室ハイキング(関東近郊)+企業研究所の見学会. GW:研究室ハイキング(関東近郊)+企業研究所の見学会. 5月末:高分子学会年次大会で発表. 5月末:高分子学会年次大会で発表. 6月初:繊維学会春期大会で発表. 6月初:繊維学会春期大会で発表. 6月頃:研究室同窓会 兼 先輩達と語る会. 6月頃:研究室同窓会 兼 先輩達と語る会. 6月末:光化学・若手の会で発表. 6月末:光化学・若手の会で発表. 7月:夏季セミナー (草津、日光、富士五湖周辺など). 7月:夏季セミナー (草津、日光、富士五湖周辺など). 8月:東工大工学系 MISW(学内の国際学生WS)でM1が英語発表. 8月:東工大工学系 MISW(学内の国際学生WS)でM1が英語発表. 9月:光化学討論会・高分子討論会で発表. 9月:光化学討論会・高分子討論会で発表. 10月:国際学会(アジアかヨーロッパ)で英語発表. 10月:国際学会(アジアかヨーロッパ)で英語発表. 11月:AOTULE国際会議(アジア圏)でM1が発表. 11月:AOTULE国際会議(アジア圏)でM1が発表. 12月:中日ポリイミド会議・日本ポリイミド・芳香族系高分子会議で発表. 12月:中日ポリイミド会議・日本ポリイミド・芳香族系高分子会議で発表. 12月:年末報告会+忘年会. 12月:年末報告会+忘年会. 1月:新年会+博士論文発表ご苦労さん会 1月:新年会+博士論文発表ご苦労さん会 1月:東アジアの大学と学生ワークショップ (B4も英語発表). 1月:東アジアの大学と学生ワークショップ (B4も英語発表). 2月~3月:修士論文+学士論文発表ご苦労さん会・卒業式. 2月~3月:修士論文+学士論文発表ご苦労さん会・卒業式. |
||||||
|
|
|||||||
| 研究日程 |  (原則として)カレンダーどおりです.研究室の定期的な公式行事(報告会・雑誌会・ミーティングなど)を土日に入れることはほぼありませんが、土日のどちらかは自宅で勉強することを推奨しています(チェックはしませんが,物性系の研究は基礎的な勉強が大切です).学会や研究会、リクレーション(ハイキングや企業見学会)、夏季セミナー等が重なってしまった場合は、研究室の都合を優先してもらいますが、そのようなことは稀です. (原則として)カレンダーどおりです.研究室の定期的な公式行事(報告会・雑誌会・ミーティングなど)を土日に入れることはほぼありませんが、土日のどちらかは自宅で勉強することを推奨しています(チェックはしませんが,物性系の研究は基礎的な勉強が大切です).学会や研究会、リクレーション(ハイキングや企業見学会)、夏季セミナー等が重なってしまった場合は、研究室の都合を優先してもらいますが、そのようなことは稀です. 土日に研究室に来るのは自由ですが,安全管理ができないので、教員がいない場合(平日の夜間を含む)は、合成実験や加熱をともなう実験はしないことにしています.学生の希望で土日や夜間にそれらの実験が必要な場合は、教員が在室するようにします. 土日に研究室に来るのは自由ですが,安全管理ができないので、教員がいない場合(平日の夜間を含む)は、合成実験や加熱をともなう実験はしないことにしています.学生の希望で土日や夜間にそれらの実験が必要な場合は、教員が在室するようにします. 夏休みと春休みは事前申告制です.海外研修や自己啓発(例えば, 1人での自由海外旅行)であれば、別途,特別休暇を認めています.夏期休暇を利用した海外への研修旅行(海外インターンシップ,IAESTEや短期留学など)や見聞を広める個人での海外旅行、企業へのインターンシップ、教育実習、危険物取扱者などの資格取得も奨励しています. 夏休みと春休みは事前申告制です.海外研修や自己啓発(例えば, 1人での自由海外旅行)であれば、別途,特別休暇を認めています.夏期休暇を利用した海外への研修旅行(海外インターンシップ,IAESTEや短期留学など)や見聞を広める個人での海外旅行、企業へのインターンシップ、教育実習、危険物取扱者などの資格取得も奨励しています. 研究室で派遣する海外研修・共同研究の費用はすべて研究室で支給しますので,自己負担はありません.海外に行く機会が必ずあるので,英語は勉強しておこう. 研究室で派遣する海外研修・共同研究の費用はすべて研究室で支給しますので,自己負担はありません.海外に行く機会が必ずあるので,英語は勉強しておこう. |
||||||
|
|
|||||||
| 研究時間 |  研究室のコアタイムは、朝9:30から夕方17:30で、この時間は研究室で研究活動に専念することにしています(遠距離通学者は,朝10時から).午前中にできるだけ研究を進め、夜は早めに帰宅する習慣を身につけることが大切です. 研究室のコアタイムは、朝9:30から夕方17:30で、この時間は研究室で研究活動に専念することにしています(遠距離通学者は,朝10時から).午前中にできるだけ研究を進め、夜は早めに帰宅する習慣を身につけることが大切です. 週に2回(火曜日と木曜日)は、16:45 から研究室の報告会と雑誌会+雑誌紹介があります.これ以外の時間は,原則として自主管理です. 週に2回(火曜日と木曜日)は、16:45 から研究室の報告会と雑誌会+雑誌紹介があります.これ以外の時間は,原則として自主管理です. 週の初め(おもに月曜日)は、朝 9:45から研究室(居室+実験室)と自分の周囲の掃除をやります.”お寺の修行”と同様,研究室や実験環境をきれいにすることは、心を整えることに繋がります.なお,4年生には+ゴミ捨てをやってもらっています. 週の初め(おもに月曜日)は、朝 9:45から研究室(居室+実験室)と自分の周囲の掃除をやります.”お寺の修行”と同様,研究室や実験環境をきれいにすることは、心を整えることに繋がります.なお,4年生には+ゴミ捨てをやってもらっています. 週の初め(おもに月曜日)の朝10時から、サブグループミーティングをやっています.サブグループごとに集まり、先週の結果と考察を述べ、全体の進捗状況を報告して、今週の研究予定を確認します. 週の初め(おもに月曜日)の朝10時から、サブグループミーティングをやっています.サブグループごとに集まり、先週の結果と考察を述べ、全体の進捗状況を報告して、今週の研究予定を確認します. 夏休み前までは、4年生の基礎勉強とSGメンバーの基礎的な勉強の場として、大学院生が講師となって輪講+勉強会を毎週やっています. 夏休み前までは、4年生の基礎勉強とSGメンバーの基礎的な勉強の場として、大学院生が講師となって輪講+勉強会を毎週やっています. 大学院生には、Lゼミのチュータや研究室見学の対応をお願いしています. 大学院生には、Lゼミのチュータや研究室見学の対応をお願いしています. |
||||||
|
|
|||||||
| 2023年度 新M1,B4のための 研究テーマプラン |
基本的には各人の希望と適性、将来展望(短期的には修士・博士課程でも続けるかどうか)を見て概ねGW前までに決定します.以下の中で面白そうと思えるテーマがあれば、事前に希望を述べてもらって結構です.また、博士課程に進学したい学生は、多少リスクが高くても永く研究をやっていけそうな新規性&オリジナリティの高いテーマに取り組んでもらいます. (以下は、安藤研の想定テーマです.石毛研の想定テーマは、研究室紹介で説明されますが、別途、問いあわせてください)  植物由来原料から合成される新規バイオベースポリイミドの合成と構造・物性評価. 植物由来原料から合成される新規バイオベースポリイミドの合成と構造・物性評価. 可視長波長域に蛍光・燐光発光を示す耐熱性透明発光材料の分子設計と太陽光スペクトルコンバータへの応用. 可視長波長域に蛍光・燐光発光を示す耐熱性透明発光材料の分子設計と太陽光スペクトルコンバータへの応用. 室温燐光性ポリイミドへの超高圧(~10万気圧)印加により引き起こされる光物性変化の振動分光法による解析. 室温燐光性ポリイミドへの超高圧(~10万気圧)印加により引き起こされる光物性変化の振動分光法による解析. 剛直構造を有するポリイミドの異方的な熱膨張率(CTE)制御を基盤とする熱光学係数ゼロポリマーの開発. 剛直構造を有するポリイミドの異方的な熱膨張率(CTE)制御を基盤とする熱光学係数ゼロポリマーの開発. 局所運動を規制した含フッ素ポリイミドの分子設計と高周波(10~20 GHz)における誘電特性. 局所運動を規制した含フッ素ポリイミドの分子設計と高周波(10~20 GHz)における誘電特性.”高機能性ポリマーの解析・設計技術”を深く探究することで、独自の視点から社会に貢献していこう. |
||||||
|
|
|||||||
| (せっかく東工大に 来たのだから) 博士号をとって 研究者・技術者になりませんか? |
(★安藤教授の定年退職時期が近いため、安藤研の博士課程学生の新規募集は 2023年4月 が最後になります.石毛研究室はその後も継続して募集します) 安藤研では、”大学や研究所でのアカデミックポジションを目指す人”だけでなく、企業の研究所などで多面的な実力を発揮できる”修士号や博士号を持った研究者・技術者”の養成を目指しています. 安藤研では、”大学や研究所でのアカデミックポジションを目指す人”だけでなく、企業の研究所などで多面的な実力を発揮できる”修士号や博士号を持った研究者・技術者”の養成を目指しています. 欧米の化学・材料系企業では、研究員の8割以上が博士号を持っているのに対し、日本の化学系企業では1割以下と言われています.しかし、現代社会で要求されている高度に機能化された物質・材料を開発する上で、修士課程までの教育・研究では必ずしも十分とは言えません. 欧米の化学・材料系企業では、研究員の8割以上が博士号を持っているのに対し、日本の化学系企業では1割以下と言われています.しかし、現代社会で要求されている高度に機能化された物質・材料を開発する上で、修士課程までの教育・研究では必ずしも十分とは言えません. 博士課程では、自分のアイデァを明確化して研究計画を立案し、研究を準備して実行し、そして成果が得られたら知的財産権を確保しつつ、学会発表+論文執筆する、という研究の一連の流れを、主体的に実行することが求められます.また,自分の研究を”高分子科学の基礎”に立ち戻って再構成し,それを跡づける作業が必要となります.このような基礎的訓練を大学でやってきたかどうかは、社会に出てしばらくしてから,”圧倒的な実力差”として現れてきます. 博士課程では、自分のアイデァを明確化して研究計画を立案し、研究を準備して実行し、そして成果が得られたら知的財産権を確保しつつ、学会発表+論文執筆する、という研究の一連の流れを、主体的に実行することが求められます.また,自分の研究を”高分子科学の基礎”に立ち戻って再構成し,それを跡づける作業が必要となります.このような基礎的訓練を大学でやってきたかどうかは、社会に出てしばらくしてから,”圧倒的な実力差”として現れてきます. 私の世代までは、博士課程を出てから企業や国公立研究所に行っても、目に見えるカタチでのメリットはほとんどありませんでした.そのような状況は早急に改善されつつあります.また、博士号を持っていることで、海外の研究者・技術者(その多くが博士号保持者)と対等な立場で議論できることも重要です.日本ではこれまで平等主義が徹底され,実力さえあればそれなりに評価されてきましたが(それ自体はとてもすばらしいことです),日本を除くグローバルな世界ではそれが常識とは言えません.個人の研究能力には”学位(博士号)という公的な裏付けが必要”と考えられています.(8大学連合パンフ:「グローバル時代にこそ博士人材」を読んでみよう) 私の世代までは、博士課程を出てから企業や国公立研究所に行っても、目に見えるカタチでのメリットはほとんどありませんでした.そのような状況は早急に改善されつつあります.また、博士号を持っていることで、海外の研究者・技術者(その多くが博士号保持者)と対等な立場で議論できることも重要です.日本ではこれまで平等主義が徹底され,実力さえあればそれなりに評価されてきましたが(それ自体はとてもすばらしいことです),日本を除くグローバルな世界ではそれが常識とは言えません.個人の研究能力には”学位(博士号)という公的な裏付けが必要”と考えられています.(8大学連合パンフ:「グローバル時代にこそ博士人材」を読んでみよう) 一昔前までは”外国”と言えば欧米のことであり,日本の技術者が欧米の技術者と直接的な交渉を持つことは多くありませんでした.しかし今,日本の産業界では”外国”の定義は東アジア圏(韓国・台湾・中国),東南アジア(香港・シンガポール・タイ),そして中東 (サウジアラビアなどの産油国) に変わってきており,しかも”外国”との交渉なしに研究・開発の仕事は成り立ちません.これらの国々の技術者の多くは,欧米や日本の大学で博士号を取得した人達ですから,彼らに伍していくには,研究・開発力だけでなく,英語力や人間力も対等,またはそれ以上であることが求められます.これらの点からも,ぜひ博士課程への進学(の可能性)を考えてみて下さい。 一昔前までは”外国”と言えば欧米のことであり,日本の技術者が欧米の技術者と直接的な交渉を持つことは多くありませんでした.しかし今,日本の産業界では”外国”の定義は東アジア圏(韓国・台湾・中国),東南アジア(香港・シンガポール・タイ),そして中東 (サウジアラビアなどの産油国) に変わってきており,しかも”外国”との交渉なしに研究・開発の仕事は成り立ちません.これらの国々の技術者の多くは,欧米や日本の大学で博士号を取得した人達ですから,彼らに伍していくには,研究・開発力だけでなく,英語力や人間力も対等,またはそれ以上であることが求められます.これらの点からも,ぜひ博士課程への進学(の可能性)を考えてみて下さい。 私の研究室では、博士課程の学生が狭い研究分野に閉じこもることなく、社会に出たときに即戦力となるような幅広い教養とコミュニケーション能力も身につけてもらうような教育を目指しています.すでにわれわれの研究室の博士課程を卒業して企業で活躍している研究者も15人に増えました(R03年現在).安藤研を希望する諸君には、ぜひ博士号(Ph.D)を取得し,幅広い実力と(独りよがりでない)
自尊感情(Self esteem)を得て、社会で大活躍して欲しいと考えています。一方,博士号の意義は認めつつも,修士課程の延長線上の研究をあと3年やるのは長すぎるな,と思う諸君は,博士課程でぜひ新しい分野にチャレンジしてほしいと思います.理由がハッキリしていれば,博士課程進学時に他の研究室に移籍することも問題ありません. 私の研究室では、博士課程の学生が狭い研究分野に閉じこもることなく、社会に出たときに即戦力となるような幅広い教養とコミュニケーション能力も身につけてもらうような教育を目指しています.すでにわれわれの研究室の博士課程を卒業して企業で活躍している研究者も15人に増えました(R03年現在).安藤研を希望する諸君には、ぜひ博士号(Ph.D)を取得し,幅広い実力と(独りよがりでない)
自尊感情(Self esteem)を得て、社会で大活躍して欲しいと考えています。一方,博士号の意義は認めつつも,修士課程の延長線上の研究をあと3年やるのは長すぎるな,と思う諸君は,博士課程でぜひ新しい分野にチャレンジしてほしいと思います.理由がハッキリしていれば,博士課程進学時に他の研究室に移籍することも問題ありません. 近い将来に対する自らのビジョンが明確であれば、修士卒で就職することもたいへん結構です.われわれの研究室の卒業生の8割は修士卒ですし、それぞれにみな社会で活躍しています. 近い将来に対する自らのビジョンが明確であれば、修士卒で就職することもたいへん結構です.われわれの研究室の卒業生の8割は修士卒ですし、それぞれにみな社会で活躍しています. 一方、博士号を取得するために会社を休職・退職して研究室に戻ってきた学生もいます.それなりのリスクはありますが、社会を広く知ってから、再び勉強するために大学に戻ってくる、というカタチはとても好ましいと思います.なお,その後の就職は問題ありません.博士卒であれば,10月採用も十分に可能です. 一方、博士号を取得するために会社を休職・退職して研究室に戻ってきた学生もいます.それなりのリスクはありますが、社会を広く知ってから、再び勉強するために大学に戻ってくる、というカタチはとても好ましいと思います.なお,その後の就職は問題ありません.博士卒であれば,10月採用も十分に可能です. |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||