| 固体19F MAS NMR法による機能性含フッ素高分子の分子構造と分子運動性の解析 |
|
|
含フッ素高分子は一般に耐熱・耐寒性、耐薬品性、耐候性などに優れ、難燃性、絶縁性、低摩擦性、非粘着性といった特性を有する材料です。高分子材料の物性は、その分子構造や分子運動性と深い関わりがあります。従って、固体状態で使用されることの多い高分子材料の物性評価には、固体中における分子の構造情報が不可欠です。
また、一般に高分子材料は、秩序構造をもたない非晶相であるか、結晶化していても結晶化度が低いことが多いため、結晶相の構造解析に有効なX線回折法からの情報にはしばしば限界があります。これに対し、固体NMR法は静磁場中の核スピンを観測することから、必ずしも秩序構造を必要とせず、結晶相のみならず非晶相に関して詳しい情報が得られるという特長を有しています。さらに、高分子の分子運動性の評価に対しては、熱物性と力学物性の測定が一般的ですが、固体NMRを用いれば広い周波数範囲において非破壊での評価が可能となります。これまでの固体NMRを用いた解析は13C 核の観測が圧倒的に主流でしたが、含フッ素高分子材料に限れば、13C核よりも19F核を観測した方が感度や分解能の点で有利です。つまり、固体19F MAS NMR法は、機能性材料に多い非晶性含フッ素高分子と、優れた耐熱性や機械特性を有する半結晶性含フッ素高分子のどちらの材料に対しても、固体13C NMR法を含めた他の分光法では得られなかった、新たな情報を獲得できる可能性を秘めており、その意義はきわめて大きいと言えます。 |
- 関連文献 -
龍野宏人, 安藤慎治, 高分子論文集, 60, 145 (2003).
|
 |
非晶性全フッ素化高分子の解析 |
|
|
| 現在、短波長レジスト向けに開発されている材料の多くが非晶性の含フッ素高分子ですが、いずれも繰り返し単位にフッ素化された脂肪族環を有しています。そのような特徴をもつ材料の先駆けといえるのが、旭硝子のCYTOP(サイトップ:右図A)です。CYTOPは、紫外〜赤外の広い波長範囲で透過率90%以上を有し、加工性にも優れるため、プラスチック光ファイバーのクラッドをはじめ光学・電子材料への応用が進んでいます。このような特性は、一価元素の全フッ素化と脂肪族環の導入によりもたらされていますが、反面、多様な立体構造のために溶液NMR法による構造解析は困難で、詳細は未だに明らかではありません。私たちは固体19F MAS NMR法により、環の根元及び先端のフッ素(図Aで順に緑、紫で表示)の信号は、立体配置の違いが反映される溶融状態(図C上)でも、立体配座の違いが強く反映される固体状態(図C下)でも複数観測されることを見出しました(☆、★)。そして、これらは立体異性を考慮したモデル化合物(図B)の量子化学計算結果とよく一致することから、主鎖には多様な立体配置が、環には多様な立体配座が存在し、それにより非晶性が発現したことが示唆されました。また、分子運動性が反映される磁気緩和時間測定から、ガラス転移点(108℃)を超えると環部位の分子運動が主鎖部位よりも先に活発化することを見出しました。 |
|
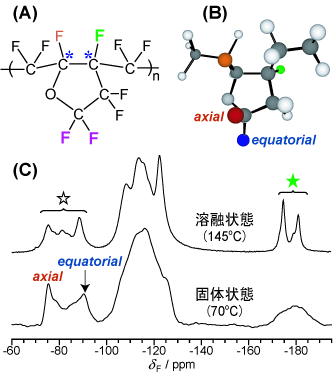 |
.
-関連発表 -
龍野宏人, 相見敬太郎, 安藤慎治, 第52回高分子年次大会予稿集,52(3),391 (2003).
龍野宏人, 相見敬太郎, 加藤悦子, 安藤慎治, 第42回NMR討論会講演要旨集, 420 (2003). |
|
 |
結晶性含フッ素高分子の解析 |
|
|
ポリエチレンの水素原子が全てフッ素原子に置換された化学構造をもつポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、テフロンの商標でお茶の間にも広く知られています。ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)とはPTFEのモノマー単位(-CF2-CF2-)中のフッ素原子1つが塩素原子に置換された高分子(-CF2-CFCl-)ですが、PTFEに匹敵する耐熱性のほか、PTFEより優れた耐寒性や寸法安定性を示します。さらに、PCTFEは半結晶性高分子ですが、加工温度の制御により結晶化度を約30%まで低減でき、成膜すると可視光に対して透明で、かつ気体透過性の著しく低い(防湿性は市販の高分子材料中で最高)フィルムとなるため、薬剤のパッケージをはじめラミネートフィルムとして広く使われています。
PTFEとPCTFEの違いは、塩素原子の導入による分子鎖のコンホメーションや分子間パッキングの変化に起因すると考えられていますが、その詳細は明らかとなっておらず、固体19F MAS NMR法による解析を試みました。右図Aに示した3種類のスペクトルはいずれも100℃で測定したもので実線は全ての19F核の寄与からなりますが、測定法を最適化することにより結晶部(点線;Cr1〜4)または非晶部(破線;Am1&2)をそれぞれ選択的に観測することができました。特に結晶部選択スペクトルは、100℃以上で各信号が高周波数側(左方向)にシフトすることを見出しました。さらに、高分子の分子運動に敏感な磁気緩和時間測定を行い、非晶部の分子運動性が活発化するのは動的粘弾性のβ分散に相当する温度(約100℃)以上であり、また融点(212℃)をはるかに下回るにもかかわらず結晶部でも同時に何らかの分子運動が起こっていることを見出しました。そして以上の事実と、立体規則性を考慮したモデル化合物(図B)の量子化学計算との比較から、温度上昇に伴い、少なくともメソ体を多く含む部位で主鎖ねじれ角が小さくなる方向(ゴーシュ方向)へのコンホメーション変化が結晶部でも起こっていることが示唆されました(図C)。 |
|
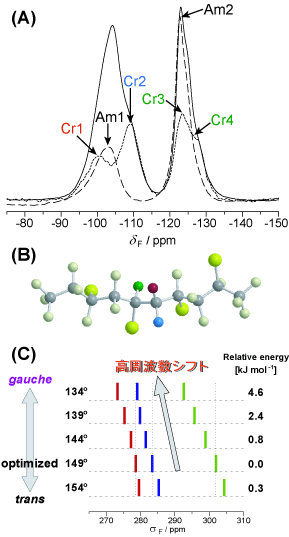 |
-関連発表 -
Hiroto Tatsuno, Keitaro Aimi, Shinji Ando, PPS-2004 Asia/Australia Meeting.
龍野宏人, 相見敬太郎, 安藤慎治, 第53回高分子討論会予稿集, 53(2), 5080 (2004).
龍野宏人, 相見敬太郎, 安藤慎治, 第43回NMR討論会講演要旨集, 374 (2004). |
|
|
|
| 固体1H → 19F CP/MAS NMR法による含フッ素化合物/シクロデキストリン包接錯体の構造解析 |
|
|
|
| シクロデキストリン(CD)は、グルコース残基が環状に連なったオリゴ糖で、右の絵のように、底の抜けたバケツあるいはドーナツに例えられるような形をしています。CDの最大の特徴は、その空孔内にさまざまな化合物をゲストとして包接し、ホスト-ゲスト錯体を形成することです。テフロンの低分子モデルというべき長鎖パーフルオロアルカンの場合、グルコース残基数7のβ-CD(内径約6Å)に覆われるように錯体を形成する(右図)ことがわかっています。ここで気になるのが、CD錯体中でパーフルオロアルカンはどのようなコンホメーションをとり、どのような分子運動が支配的なのかということです。しかし固体状態の含フッ素化合物/CD錯体系で、そのような議論はこれまでほとんどされていません。そこで私たちは、含フッ素高分子材料の解析で培ってきた固体NMRの手法・技術をこの系にも適用し、分子レベルの情報の抽出を試みています。まず、水素核から炭素核への磁化移動(CP)を利用した1H→13C CP/MAS法により、ホストCDを選択的に観測することができます。同様に19F→13C CP/MAS法を用いると、ゲストパーフルオロアルカンのみを観測し、その分子運動性が評価できます。さらにゲスト分子の構造に関する詳細な情報は19F MAS法および1H→19F CP/MAS法から得られます。特に後者のスペクトルが容易に得られることから1Hを有するホストと19Fを有するゲストが確かに数Åの距離で近接していることがわかります。右に示したのは、単体およびβ-CD錯体中n-C9F20の固体19F MAS NMRスペクトルです。包接により信号がシフトし、スペクトル線形も変化していることがわかります。さらに、スペクトル線形や磁気緩和時間の温度変化から、熱分析などでは検知の困難な分子運動の変化を見出そうと試みています。 |
|
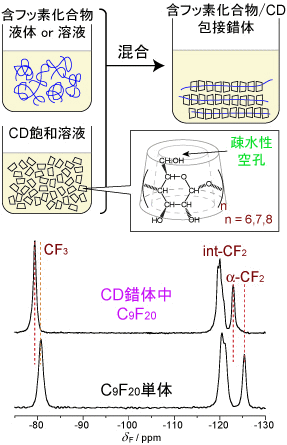 |
-関連発表 -
龍野宏人, 安藤慎治, 第54回高分子年次大会, 54(1), (2005). |
|