- 関連文献 -
1) 関野 裕幸, 浦野 裕一, 植竹 和幸, 安藤 慎治, 高分子学会予稿集, 53(1), 1543
(2004).
2) 化学工業日報新聞記事
3) 日刊工業新聞新聞記事
4) Hiroyuki SEKINO, Yuichi URANO, Shinji ANDO, China-Japan Seminar on Advanced
Aromatic & Condesation Polymers (Hangzhou, China) (2004). |
|
|
高蛍光性ポリイミドの発光機構や動的挙動には未だに不明な点が多くあります。時間分解蛍光測定を用いて、電荷移動(CT)蛍光と酸無水物部分の局所的な電子の遷移に基づく蛍光(LE蛍光)の発光機構の解析を試みました。
LE蛍光しか存在しないポリイミドでは、LE蛍光はナノ秒単位の寿命を有しています。一方、CT蛍光とLE蛍光が存在するポリイミドでは、LE蛍光はピコ秒単位の寿命を有しています。LE蛍光とCT蛍光が存在するポリイミドでは、LE蛍光に比べCT蛍光の蛍光減衰曲線に明確な’遅れ’が存在しており、これは励起LE状態から励起CT状態への電子の移動が起こっていること示唆しています。そのため励起LE状態の電子は見かけ上、速く消滅するので、LE蛍光しか存在しないポリイミドよりもLE蛍光の寿命が短くなっていると考えられます。
|
|
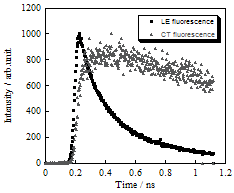 |
|
- 関連文献 -
1) 関野 裕幸, 浦野 裕一, 浅野 素子, 海津 洋行, 安藤 慎治, 高分子学会予稿集,
53(2), 4670 (2004).
2) 関野 裕幸, 浦野 裕一, 浅野 素子, 海津 洋行, 安藤 慎治, 日本ポリイミド・芳香族系高分子会議要旨集,
13, 23 (2004). |
|
|
|
 |
|